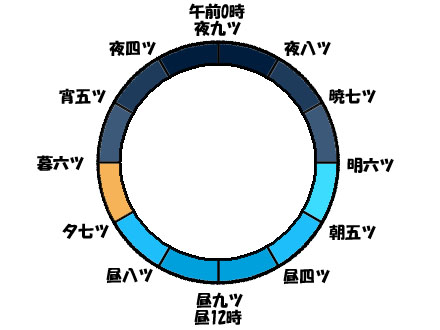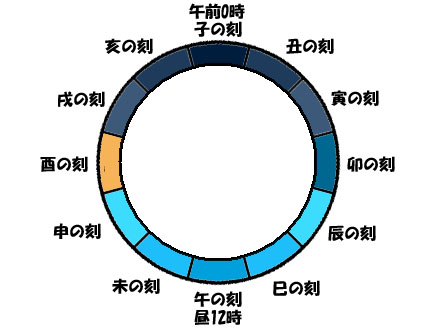時刻
時そばの中に、「今ぁ、何刻だい?」
「へぇ、九ツで・・・」。
これをまねした男、次の日早いうちからそば屋を探し、「今ぁ、何刻だい?」とやると、
そば屋は「へぇ、四ツで・・・」
いくら早いうちといっても、九ツを四ツってぇのは・・・。
と現代では考えてしまいますが、ここが昔の時間の数え方の面白い(難しい)とこで。
いくら早いうちといっても、九ツを四ツってぇのは・・・。
と現代では考えてしまいますが、ここが昔の時間の数え方の面白い(難しい)とこで。
江戸時代、刻の数え方は、日の出を「明六ツ(あけむつ)」、
日の入りを「暮六ツ(くれむつ)」として、この間を、昼夜でそれぞれ
六分割して、「 明六ツ、朝五ツ、昼四ツ、昼九ツ(正午=お天道さんが真上にくる刻限)、
昼八ツ(おやつ)、夕七ツ、暮六ツ、宵五ツ、夜四ツ、夜九ツ、夜八ツ、暁七ツ(お江戸日本橋七ツ発ち)
」とします。
日の出から、日の入りで時間を分割していたので、季節によって、その間隔は変って きますが、大雑把な図で表すとこんな感じになります。
日の出から、日の入りで時間を分割していたので、季節によって、その間隔は変って きますが、大雑把な図で表すとこんな感じになります。
(余談ですが、この時代、夏はみんな寝不足だったのでは?とか考えてしまう今日この頃)
つまり、九ツというのは、現在の午前0時(夜九ツ)のことで、先の男が夜九ツの鐘を聞いた
後で「何刻だい?」とやったのに対して、後の男は夜九ツを待ちきれずに
「何刻だい?」をやってしまったと云うわけで。
また、時刻を十二支に準えて呼ぶ場合もあり、こんな感じです。
昼の12時を正午というのはここから来ています(ちなみに、こちらはあまり使いませんが、
午前0時は正子(しょうし)といいます)。
ところで、江戸時代は一日の考え方も、現在とは少々違っていたようで、日の出から
次の日の出までを一日と考えていたようです。
この習慣を、うかがうことができるものに、年末恒例の「忠臣蔵」があります。 赤穂浪士が吉良邸に討ち入ったのは12月14日とされますが、 これは現在の時刻でいうと、12月15日午前4時頃(日の出前)だったそうです。
となると、一月一日午前0時のカウントダウン後、そのまま初詣。ということが よくありますが、あれは、世が世なら詣で納めってことになるのでしょうかねぇ?
この習慣を、うかがうことができるものに、年末恒例の「忠臣蔵」があります。 赤穂浪士が吉良邸に討ち入ったのは12月14日とされますが、 これは現在の時刻でいうと、12月15日午前4時頃(日の出前)だったそうです。
となると、一月一日午前0時のカウントダウン後、そのまま初詣。ということが よくありますが、あれは、世が世なら詣で納めってことになるのでしょうかねぇ?